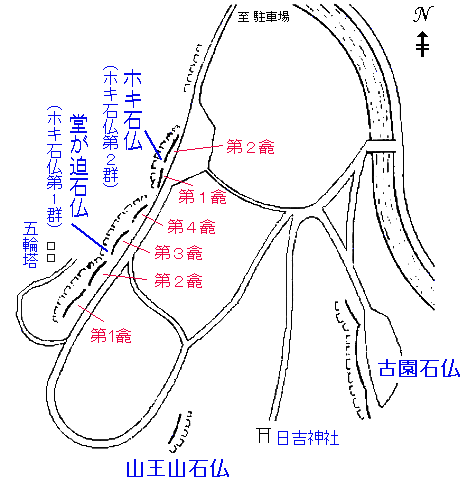私が、初めてこの臼杵石仏を見たのは、1979年、本格的な保存修復工事が始まる前、美術書で見た臼杵石仏と富貴寺阿弥陀堂の見学を目的で訪れた3泊4日の旅行が最初である。その時の臼杵石仏の印象は、「美術書どおり、すばらしい仏像であった。」といったところである。 実は、この3泊4日の旅行が私の石仏遍歴の原点となるのであるが、それは臼杵石仏を見たからではなく、岩そのもののであるかのように迫ってくる岩と仏が一体となった熊野磨崖仏を見たからである。「国東半島と豊前の磨崖仏」で述べたように、私にとって、石仏・磨崖仏の魅力は「岩(石)の持つ美しさ・厳しさと人々の信仰心が結びついた、造形美」にある。
古園石仏の大日如来とホキ石仏の阿弥陀三尊で代表される臼杵石仏は平安後期を代表する仏像である。しかし、熊野磨崖仏を見た後のためか、木彫仏と同じような鑿あとの冴えた丸彫りに近い表現のためか、岩(石)の持つ美しさ・厳しさをその時はあまり感じなかった。その意味では、私にとっては臼杵石仏は奈良の寺院の仏像と同じであった。
しかし、仏像としての魅力は忘れがたく、1979年以降、4回、訪れた。
2回目に訪れた時は、絶好の天気で、ホキ石仏の阿弥陀三尊は陽に映え、すばらしい姿を見せていた。おだやかな中に厳しさを見せる阿弥陀如来の顔が印象的であった。岩の前に置かれた古園の大日如来の仏頭も、岩の生命がこぼれ落ちた仏頭に凝縮されたような、力強さを感じた。そこには、「岩の仏」としての存在感があった。「岩(石)の持つ美しさ・厳しさと人々の信仰心が結びついた、造形美」を見たような気がした。
一番最近、訪れたのは、一連の修復工事が終わり、各磨崖仏に覆堂が設けられていた1996年であった。しかし、その時は2回目の時、味わった感慨がわいてこなかった。特に、ホキ石仏の阿弥陀三尊は平凡な丈六の阿弥陀如来にしか見えなかった。首つながった古園石仏の大日如来は、仏頭だけの時と同じように魅力的ではあったが、整いすぎて迫力や力強さを欠くような気がした。 では、同じ石仏が、なぜこのように印象が違ったのであろうか。私はその原因は「(1)、覆堂によって入る光が少なくなり、陰影がつかず、以前のような、鑿あとの鋭さや、立体感が見られなくなったこと。(2)、修復がおこなわれ、覆堂に覆われるたことによって、岩の持つ生命感や厳しさが薄められたこと。」にあると考える。 大陸から伝わった仏教は山や川や木や石などの自然そのものを神として崇める日本古来の信仰と結びつき日本の民衆の中に広がっていった。従って、磨崖仏の制作者は岩を単に素材として仏像を彫ったわけではない、岩に神を、仏を、命を感じ、仏像を彫ったのである。 臼杵石仏は柔らかい凝灰岩を木彫と同じように丸彫りに近い厚肉彫りで彫られたもので、精緻な美しさを見せている。木彫の仏師が刻んだものではないかともいわれている。その点では、岩が素材として扱われ、「岩」の存在感は薄いといえる。 しかし、岩は長い間の時間の流れの中で風化し滅んでいく。岩に彫られた磨崖仏も例外ではない、その時間の流れの中で風化し摩滅していく。それは、岩に神を、仏を、命を感じ、彫られた「岩の仏」としての宿命ではないだろうか。私が、岩の前に置かれた古園の大日如来の仏頭に、岩の生命がこぼれ落ちた仏頭に凝縮されたような、力強さを感じた様な気がしたのは、風化し摩滅していく岩の持つ生命感をそこに感じたからではないだろうか。 臼杵石仏の作者は、永遠の慈悲と救済を願い、滅びのないみ仏を岩に刻んだのかもしれない、しかし大自然の摂理はそれを許さず、まるで木彫仏であるかのように、岩を切り刻んだ臼杵石仏は崩壊かすすんでいる。そこに、「岩の仏」としての美しさの一端があるのではないだろうか。大護八郎氏は〔『石仏の美2岩の仏』 佐藤宗太郎・大護八郎 木耳社〕の概説の最後を「壊れゆく磨崖仏だからこそ、われわれは永遠の中の時の流れを知り、変わりゆく姿の中に無上の美しさを見いだすであろう。」と結んでいる。
もちろん、日本の石仏の最高峰たる臼杵石仏は保存し、永遠の命を与える必要はあるだろう。覆堂も当然必要であり、ある意味では創建当時に創建当時に戻したといえる(創建当時は覆い堂に覆われていたと考えられる)。その意味では、現在の保存活動は当然のことといえる。しかし、私の単なる感傷であるかもしれないが、なぜか一抹の不満を感じる。 |